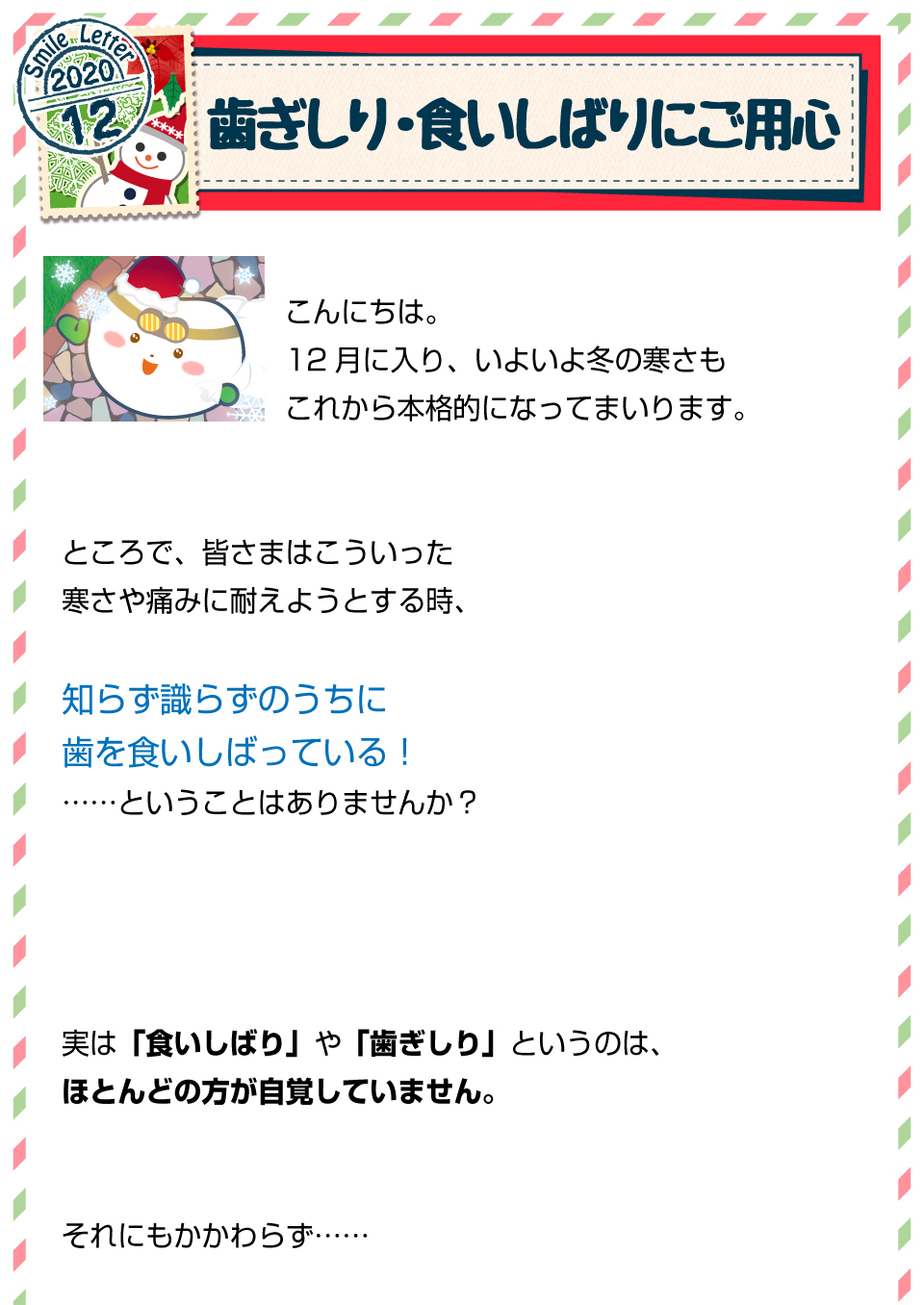



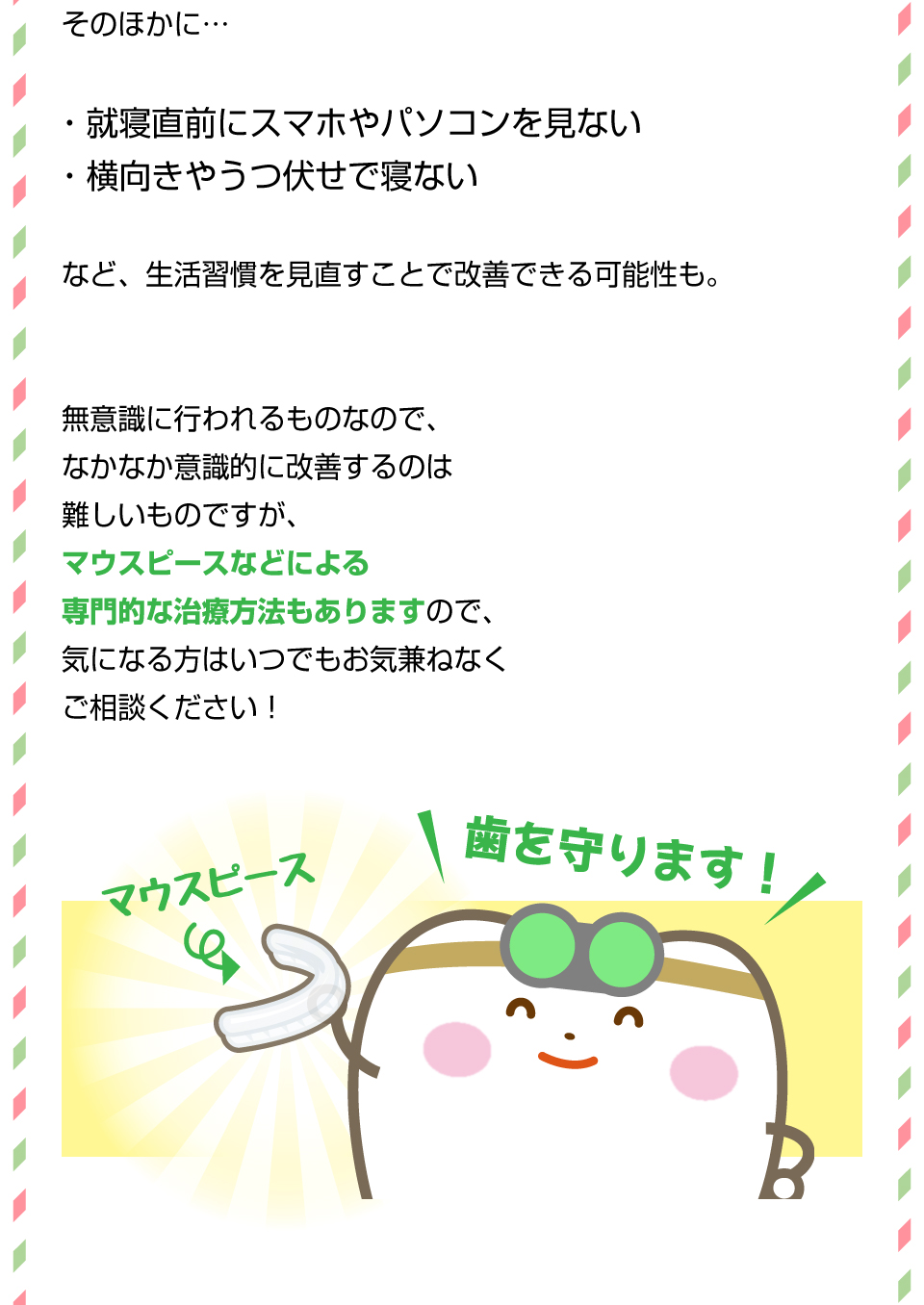

投稿者「nao」のアーカイブ
Designs For Vision の修理 終了!!
普段使用している拡大鏡 Designs For Vision 8倍が2ヶ月ぶりに手元に戻ってきました。大変気に入っている拡大鏡ですが制作・修理等は本国のアメリカで行いますので数ヶ月に時間が必要なことが多いです。今日、修理品持ってきていただいて修理代も10万円オーバー(涙)仕方がありませんが高いです・・・。今日までの修理期間中はカールツァイスの拡大鏡で頑張っていましたが明日からはDesigns For Visionに戻ります。

歯が痛いときはNGです!








☆正しい臨床決断をするためのエビデンス・ベースト・インプラントロジー
☆「正しい臨床決断をするためのエビデンス・ベースト・インプラントロジー」クインテッセン出版 小田師巳・園山亘 著
コロナ渦の中ではなかなか外に出てのセミナーが中止になったり、延期になったりと勉強する機会が削がれることが多いです。田舎の歯科医師は専門書やDVD・WEBでの勉強が中心となります。そこで、インプラントの勉強をすることも多いのですが上記の本は、インプラント治療をしている先生には是非読んでいただきたい内容が満載です。初心者の先生には少しむずかしいかもしれませんが、インプラント治療を普段の診療に取り入れている先生には勉強になることが満載です。特にインプラント治療の埋入についてではなく、埋入深度や軟組織・硬組織のアプローチ・リッジプリザベーション等について詳しく書かれています。
基本、エビデンスベースでの説明があり、実際の診療ではどうすることが良いのか?自分が行っている治療行為にエビデンスにあっているのか?様々なインプラント治療に自己流になっていないのか?等様々自分は本を通じて反省と勉強をすることができます。臨床例も多いので臨床医には助かります。また、文書が読みやすく理解しやすく読みながら「フムフム」とうなずいている自分がいました(笑)この頃は寝る前にこの本で読み直しすることが多いです。もちろんエビデンスが全てではありませんが、研究家がそれぞれ切磋琢磨して出したデータを読む力のない私にとっては噛み砕いて著名な論文を紐解いているのは勉強になります。
来年は、人気のある小田先生のセミナーを受講予定です。さらなる飛躍のためにしっかり勉強したいと思っています。オススメです。

