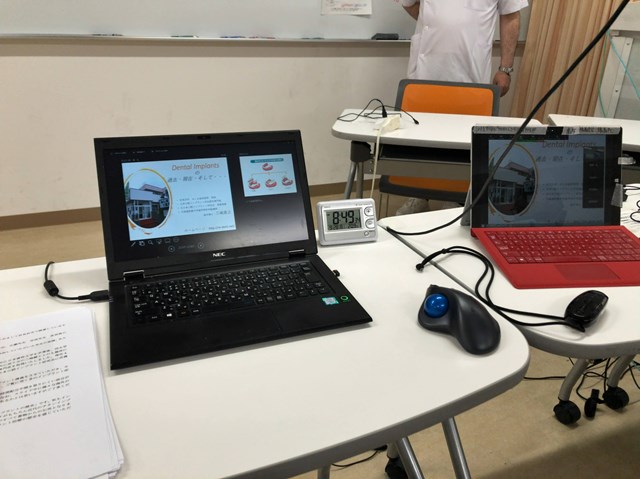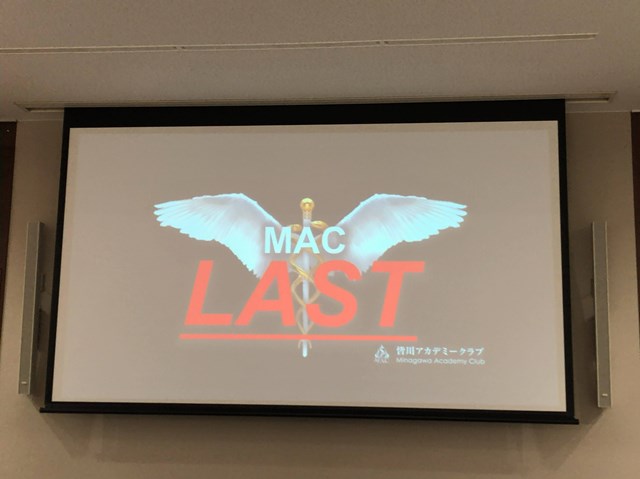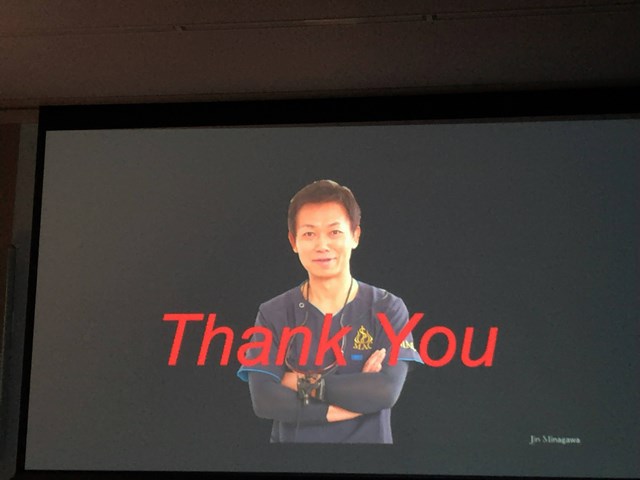今日(28日)、北海道医療大学歯学部の授業を行ってきました。昨年までは父が医療大学の授業を担当していましたが今年から私にバトンタッチです。講義の内容は「口腔インプラントの歴史」です。近代歯科インプラントの歴史は100年足らず、日本でもチタンインプラントの歴史は70年程度をいわれています。先週行われた「日本口腔インプラント学会」の大会も50回大会でした。つまり50年ですね。私もインプラントに携わって15年程度です。今回、授業はコロナ感染症の影響で直接 学生の前に立つことはなく、リモートで授業です。学生も自宅等で受講するようです。反応がわかりませんので居眠りしていてもわかりません(笑)朝9時からの授業でしたので多分 学生の方は眠かったのではないでしょうか?スライドも180枚作りましたが90分授業では多すぎたようで後半は駆け足になってしまい申し訳ありませんでした!自分のインプラント歴史を勉強でき、準備の2ヶ月間は充実した毎日でした。