皆川先生オススメの無農薬お弁当(遺伝子組換え材料ゼロ)でした!(笑)


皆川先生オススメの無農薬お弁当(遺伝子組換え材料ゼロ)でした!(笑)

19日は東京で行われた「皆川インプラントアカデミーマスターコース」1回目を受講してきました。皆川仁 先生のインプラント1年コースです。来年の4月まで開催されますがしっかりと吸収したいと思っています。1回目は切開・剥離・縫合です。しっかり豚骨実習をしてきました。少しでも患者さんにフィードバックできるように勉強したいと思います。
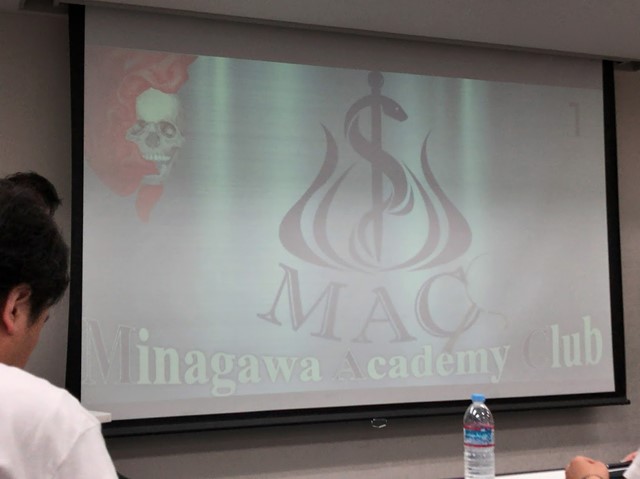




11日12日 北日本口腔インプラント研究会主催 日本口腔インプラント学会認定講習会 6月コースが開催されました。
11日 日本歯科大学 中原 貴教授、北日本口腔インプラント研究会 会長 富田 達洋先生、インプラント学会専門医 藤原 秀光先生、12日 日本歯科大学名誉教授 代居 敬先生、北海道医療大学 安彦善裕教授 でした。




